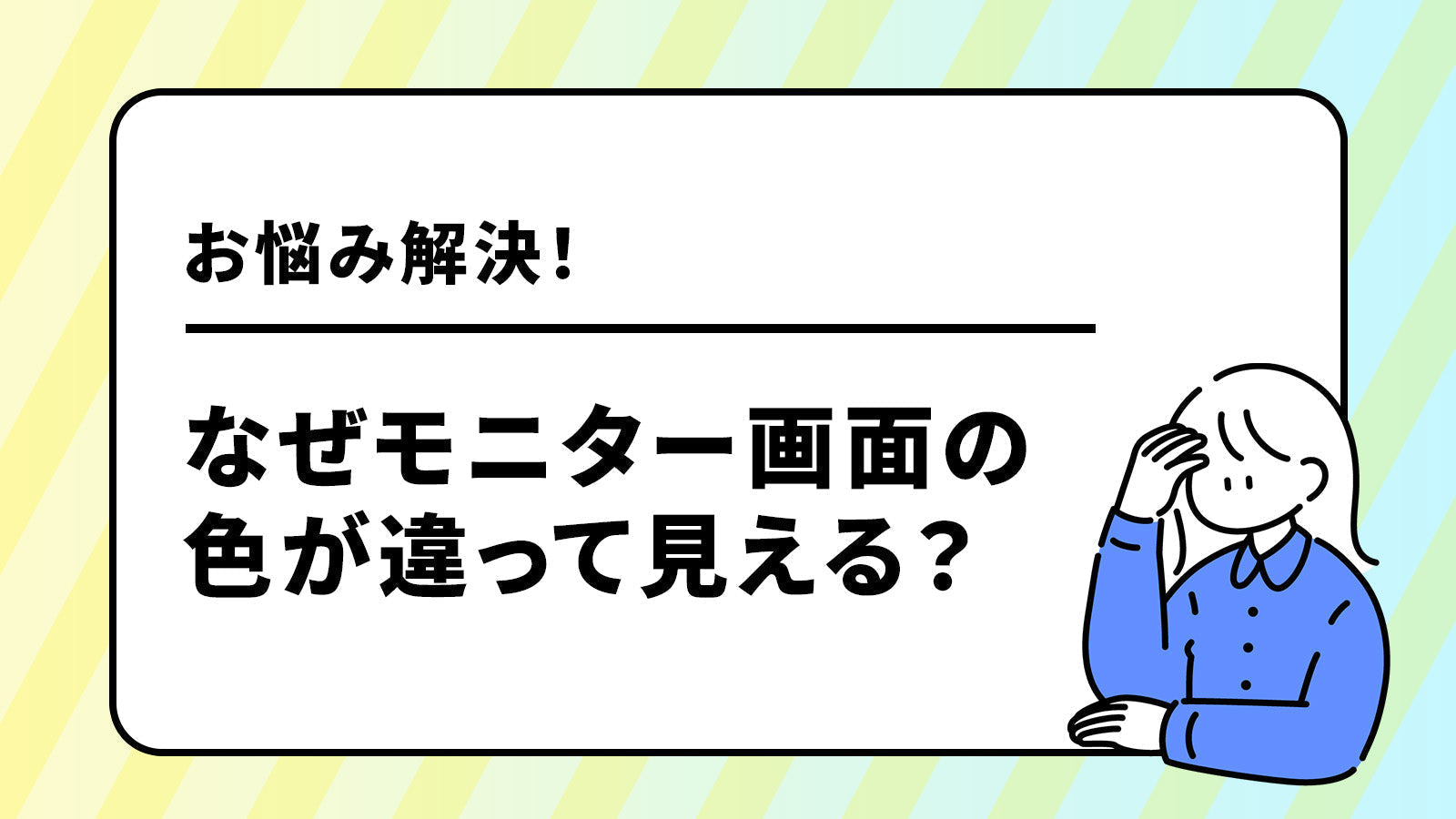
モニター画面の色がおかしい!?青っぽい・赤っぽい・黄色っぽい…色合いが違うのは何故?色の調整方法を解説
こんにちは、スタッフの川田です。
家電量販店に行った際にたくさんの液晶モニターが展示してあったりしますが、隣同士の機種で液晶画面の色が違ったり、同一機種で同じ設定にしても色が違って見えることがあります。
なぜ機種によって見え方が違うのか?詳しく解説します。
液晶画面の色の作られ方
モニターの色構成
モニターやテレビなどの発光体における色の表現は、主にRGBという表現方法を採用しています。Red(赤)、Green(緑)、Blue(青)の3つの原色を混ぜ合わせることで、様々な色彩が生まれる仕組みです。
モニターの画面は、小さなピクセルで構成されており、各ピクセルはRGBの3つのサブピクセルを持っています。これらのサブピクセルに色を割り当てることによって、様々な色が表現できます。
例えば、赤を表示する場合は、赤のサブピクセルを最大の輝度に設定し、緑と青のサブピクセルはオフにします。
また、RGBはそれぞれの光を混ぜるほど明るくなり、最終的に白になります。これを「加法混色」と言い、白色を表現するには、すべての色の値を最大値の255にします。
その逆で、すべての色の値を0にすると、黒色が表現できます。
モニターの「白」表現
モニターにおける「白色」の表現はRBGの組み合わせでされると説明しましたが、同じ数値で指定していても実際に「見える色」に違いを感じることがあります。それには「色温度」が関係しています。
色温度とは「光の色」を表すのに使われる数値のことで、単位は絶対温度の「K」(ケルビン)で示されます。このケルビンの値が低いほど「白色」が赤みを帯び、高いほど「白色」が青みを帯びます。
色温度の調整方法
最近のモニターの多くはOSDメニューで色温度を調整することが可能です。色温度の調整項目は製品によって異なりますが、大きく分けると「青系」や「赤系」、もしくは「寒色系」や「暖色系」などの言葉で選ぶものと、「6500K」や「9300K」といったような数値で設定するものがあります。

今回はPixioのモニターを例に挙げると、Warm/Normal/Coolの3種が指定できるようになっています。
モニターなどの電子機器においては青っぽい色が好まれる傾向にありますが、基本的には自分の好みの色に合わせて調整する形で問題ありません。
色の違いを感じる原因
現在、市販されているPC用モニターには、主に以下の種類が販売されています。
- TFTモニター(液晶モニター)
- LEDモニター
- 有機ELモニター(OLED)
一見同じように見えるモニターでも、構造やパネルの種類によっても色の出方が大きく違ってきます。
たとえば、同じ「白色」を表示していても、あるモニターでは青色っぽく、別のモニターでは黄色っぽく見えることがあります。
これは、以下のような要素によって決まります。
- パネルの種類(IPS/TN/VA)
- モニターの設定
- カラープロファイルの違い(sRGB/Adobe RGBなど)
- PCのグラフィック設定
- 経年劣化や使用環境(照明・視野角)
- 製造ロットによるパネルの個性の違い
パネルの種類により見え方や色味が違う
まず、液晶パネルにも色の出方が大きく異なります。
現在、液晶モニターでは、TNパネル、VAパネル、IPSパネルの3種類が使用されております。
さらに、TN・VA・IPSパネルがそれぞれ進化を続けており、上位機種となるパネルが誕生しております。
- TNパネル:TN, STN, DSTN, Fast TN など
- VAパネル:VA, Fast VA, MVA, PVA, S-PVA など
- IPSパネル:IPS, AH-IPS, Nano IPS, Fast IPS, ADS など
(ADSは商標の関係でIPSではありませんが、ここでは同一として説明します)
つまり、同じIPSパネルという表記であっても厳密には違う種類のパネルを使用していることがあり、このIPSの種類によっても透過率や色再現性に違いがあるため、まったく同じ表示にはならないということです。
また、PCやスマホのVersionのように第〇〇世代という違いが各パネルの種類にも存在しており、それぞれで細かく色の見え方が変わります。
さらに細かい話をすると、IPSやNano IPSパネルのように同じ名前であっても、厳密にはさらに細かく種類が存在しており、その中からVersionが存在しているため、考えるとキリがないほど細分化されています。
同じIPSパネルでもまったく同じバージョンや種類のパネルを使用しているわけではないため、並べてみると色味の違いがはっきり分かることがあります。
モニターの設定による違い
液晶モニターの設定には、明るさ・コントラスト・シャープネス・色温度など、さまざまな設定があり、この設定を変える事によって見え方が大きく変わってきます。
細かく1つずつ設定していくこともできますし、FPSモードや写真モードなど最初から内蔵されているプリセットモードを選んで簡単に変えることもできます。
この設定が適切に選択されていないと、違和感を感じることがあります。見にくく感じたら設定を変えてみるとよいでしょう。

カラープロファイルが違う
液晶モニターには、「カラープロファイル」という「どの方法で色を表示するか」を選んだ状態で表示されております。
主に、以下のプロファイルが一般的に広く使用されております。
- sRGB:一般的なWeb用途に使われる規格
- Adobe RGB:印刷業界で広く使われる広色域プロファイル
- Display P3:Apple製品などで使用される広色域
使用しているモニターやOSD設定で、sRGBを基準にしているか、Adobe RGBで表示しているかで、見た目の印象が大きく変わります。
PCのグラフィック設定が違う
同じモニターでも、接続するPCのOS(Windows/Mac)や、グラフィックボードの設定によって色味が変化します。特にWindowsでは「夜間モード」や「HDR」の影響で色味や明るさが変わったり、コントラストが高く表示されたりすることがあります。

↑Windowsのディスプレイ設定画面
長時間使用による輝度低下や色調のズレが発生
液晶モニターやLEDモニターはLEDライトを使用して表示しているため、このLEDライトの寿命が見え方に大きく関与します。
また、有機ELパネルのような素子自体が発光するモニターも、使用時間により劣化が発生するため、LEDライト同様に使用時間に比例して見え方が変わってきます。
ここではLEDライトを用いた液晶モニターを中心に説明を行います。
LEDライトは、使用時間によって明るさが徐々に低下し、最大輝度が低下していきます。通常の仕事や資料作成などに使う分には気づきにくいですし、気づいたとしても大きな不便は感じにくいとは思いますが、デザイン系やゲーム系の場合、3年も使えば明らかな劣化による変化が発生するため、下記で説明するキャリブレーションキットを使用するか、気になる方は買い替えたほうがよいでしょう。

製造ロットによるパネルの個性で微妙な違いが発生
液晶パネルというものは、大きなパネルで製造し、各サイズにカットして製造されております。
その際に、各ロットによって微妙に色表示が異なって製造されており、現在の技術ではまったく同じ色で製造することは困難と言われています。
そのため、まったく同じ機種でまったく同じ設定にしたとしても、横に並べた場合、若干の色味の違いが発生することがあります。
この微妙な色味の違いが業務上で支障を来たすようなデザイン系モニターの場合、出荷前にキャリブレーション設定をした上で出荷されますが、この一手間がコストアップにつながるため、デザイン系モニターが一般的なモニターに比べて高価になってしまう理由の1つになっています。
一般的なモニターでは詳細なキャリブレーション設定を行わずに出荷をしています。
そのため、この微妙な差がどうしても気になるという方は、デザイン系モニターを購入するか、3rd Party製のキャリブレーションキットを購入して調整するかの方法で対処することで、ある程度は解決します。
解決方法
この色味の違いをなくしたい場合は、主に以下の5種類の方法を試してみてもらいたいと思います。
モニター内のOSD設定で色味を調整する
液晶モニターのメニュー設定画面(OSD設定)では、輝度・コントラスト・シャープネス・色温度・色相・彩度などの設定を選べるようになっています。
この設定で、ご自身がベストと思う設定で調整してみてください。
また、ブルーライトカット機能のON/OFFやHDR機能のON/OFFでも色味は大きく変わりますので、こちらも同様にチェックしてみてください。
PCのグラフィック設定を調整する
PC内のグラフィック設定の中には、夜間モードやHDRモードなどがあります。
この設定をいつの間にか変えていることで、「あれ?いつもと色味が違う!」ということも実際に起こっているようです。
そのため、ある日突然見え方が変わった場合は、PC内のグラフィック設定を見直してみてください。
それでも変わらない場合はモニター本体を工場出荷設定モードにして一旦設定を元通りに戻してみるのも1つの方法です。
部屋の照明の色味や明るさを調整する
部屋の照明が変わるだけでモニターの色味が大きく変わって見えます。
そして、朝・昼・晩と部屋の明るさが違うと見え方が変わってきます。
また、天候により色味が違って見える事もあります。
そのため、まずは照明の色味や明るさを見直してみてください。蛍光灯の元では画面が青白く見える傾向があり、白色電球の元では画面が黄色っぽく見える傾向があります。
カラーチェッカー画像を使用する
「Color Checker(カラーチェッカー)」というカラーパターンの画像を用いて、正確な色を導き出す方法があります。
ただし、こちらは3rd Party製となるため、メーカー公式の方法とは言いづらいため、使用はユーザーご自身の責任での使用となります。
3rd Party製のキャリブレーション製品を活用する
モニターのOSD設定も調整した、PC内のグラフィック設定も見直した、部屋の照明も見直した、それでも色味が若干おかしいな…と思った場合、3rd Party製のキャリブレーションキットを購入し、色味を調整する方法もあります。
ただし、3rd Party製という事は液晶モニターメーカーの公式製品とは異なるため、使用に対しての保証がありませんので、使えるかどうかは液晶モニターメーカーとしては責任が取れません。そのため、ユーザーご自身の責任での使用となります。
まとめ
モニターの色合いが違うのは、モニターの性能、パネル方式、設定、カラープロファイル、環境要因、製造ロットの違いなど、さまざまな要素が関係しています。
簡単に色味を同じにすることは難しいですが、正しい知識と適切な設定、そしてキャリブレーションによって、かなりの精度で色を一致させることはできます。
以上、「モニター画面の色合いが違うのは何故?」を解説しました。
ぜひこの機会にモニターの設定を見直して、調整してみてくださいね!